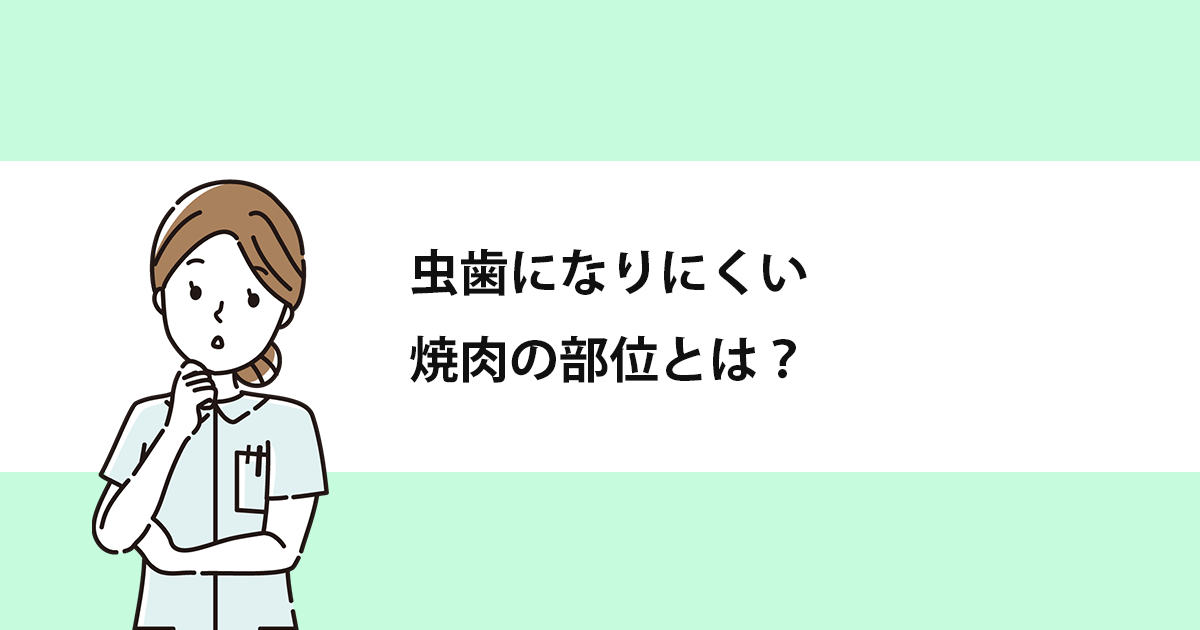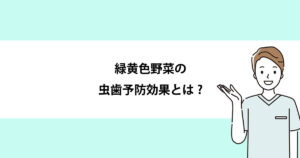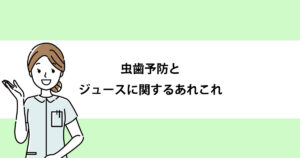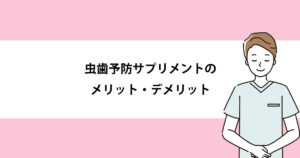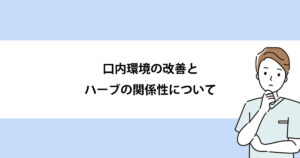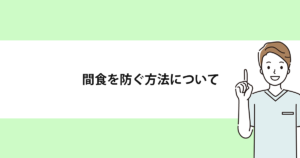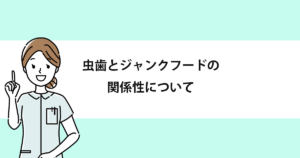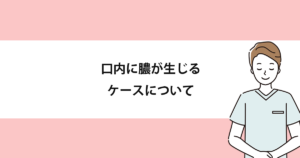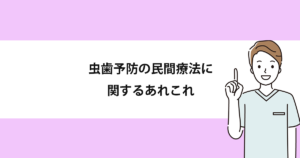日本食におけるごちそうをイメージしたとき、真っ先に焼肉が頭に浮かぶという方も少なくないかと思います。
しかし、焼肉にも当然虫歯リスクはあるため、何も考えずに食べるのは良くありません。
今回はなるべく虫歯を予防したい方に向けて、虫歯になりにくい焼肉の部位を中心に解説します。
虫歯になりにくい焼肉の部位3選
数ある焼肉の部位の中でも、以下は比較的虫歯のリスクが低いと言えます。
・赤身肉
・タン
・噛み応えのあるホルモン
各項目について詳しく説明します。
赤身肉
虫歯予防を意識しつつ焼肉を楽しみたいという方は、なるべく赤身肉を選ぶようにしましょう。
ここでいう赤身肉には、ロースやヒレ、モモなどが該当します。
脂質が多いカルビなどのお肉は、間接的に虫歯のリスクを高めることがあります。
脂質が虫歯菌のエサになる心配はありませんが、摂取量が多いと虫歯菌の働きを活発にしてしまうおそれがあるからです。
ロースは牛の背中側のお肉で、肩から腰にかけての部分です。
脂身が少ないながらもきめ細かい肉質で、やわらかく風味も良いのが特徴です。
またヒレは牛の腰のあたりにある棒状の部位で、運動量が少ないため非常にやわらかい上に、赤身が中心です。
さらにモモは、牛肉の後ろ脚の太もも部分のお肉で、ヘルシーな部位として人気があります。
タン
虫歯になりにくい焼肉の部位としては、タンも挙げられます。
タンは牛の舌のことで、焼肉においては最初に食べられることが多い部位です。
タンは歯応えがあり、しっかり噛まなければ食べられないため、必然的に咀嚼回数が増加します。
咀嚼回数が増えるということは、その分唾液の分泌されやすくなるということであり、口内の汚れが洗い流されやすくなります。
またタンには大きく分けてタン元、タン先、タン中という3つの種類があります。
もっとも虫歯予防に適していると言えるのがタン先で、こちらはタンの先端部分であり、コリコリとした食感が特徴です。
ちなみにタン元は舌の根元部分で、もっともやわらかく霜降り状になっていることが多いです。
タン中はタン先とタン元の中間の部分で、適度な歯応えと旨味が楽しめます。
噛み応えのあるホルモン
噛み応えのあるホルモンも、虫歯を予防しやすい焼肉の部位だと言えます。
具体的にはウルテやセンマイ、ミノといった部位を指しています。
ウルテは牛の喉の気管にあたる軟骨で、ホルモンの中でも特に硬い部位です。
独特のコリコリとした食感が特徴で、脂肪も少なくあっさりしているため、他の部位に比べると虫歯予防には適しています。
またセンマイは牛の第三胃袋で、内壁のヒダが多数あることからセンマイ(千枚)と呼ばれています。
こちらも低脂肪低カロリーであり、虫歯を防ぎやすい他、コラーゲンも豊富であるため歯周病予防にも効果を発揮します。
さらにミノについては、牛の第一胃袋であり、肉厚でコリコリとした食感を持っています。
素材そのものは淡泊な味ですが、さまざまな味付けとの相性が良いです。
ミノを積極的に食べることで、咀嚼回数や唾液の分泌量が増加するだけでなく、虫歯予防に必要なタンパク質やミネラル、ビタミンをバランス良く摂取できます。
焼肉の虫歯リスクを減らす食べ方について
焼肉の虫歯リスクを抑えるには、部位の選び方だけでなく食べ方についても注意しなければいけません。
具体的には、タレやお肉以外に食べるものの工夫です。
焼肉屋で提供されるお肉は、基本的にタレに長時間浸けられた状態で提供されます。
こちらを食べる際には、小皿に入れたタレに再びつけて食べることになります。
しかし、焼肉のタレには多くの糖分が含まれています。
糖分は虫歯菌のエサになり、歯を溶かす原因になるため、なるべく摂取しないことをおすすめします。
タレの量を減らすのは物足りないという方は、他の虫歯リスクが低い調味料で代用しましょう。
例えば塩やレモン汁、ワサビなどをつけて食べれば、そこまでタレを使用しなくても満足感を得られます。
また焼肉を食べる際は、お肉ばかり食べていてはいけません。
いくら脂質の少ないお肉を選んでいたとしても、そればかり食べると間接的に虫歯のリスクは高くなります。
焼肉屋には、サラダなどのサイドメニューも取り揃えられていることが多いため、バランスの良い食事内容になるようにしてください。
ちなみに、焼肉屋ではお酒を飲む方も多いですが、お酒は虫歯のリスクを高める大きな要因です。
アルコールには糖分が含まれていますし、摂取量が多くなると利尿作用が働き、身体の水分が減少して口内が乾きやすくなります。
そのため、脂っこい焼肉を食べながらお酒を飲むという行動は、なるべく習慣づけないようにするべきです。
まとめ
日々ブラッシングを徹底しておけば、十分に虫歯を予防できると考えている方も少なくありません。
もちろんブラッシングは重要な習慣ですが、焼肉など本来虫歯リスクが高いものを食べるとき、なるべくそのリスクを減らすことも大切です。
どれだけ丁寧に歯を磨いていても、食生活が乱れているとその効果は大きく減少してしまいます。