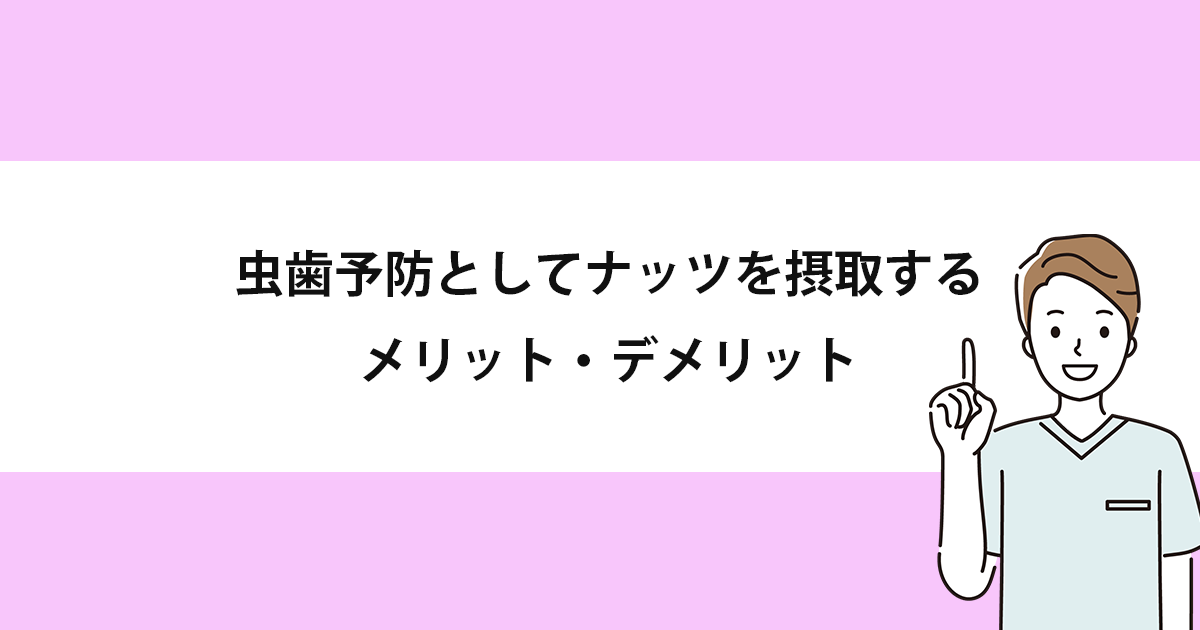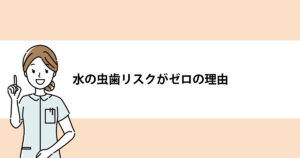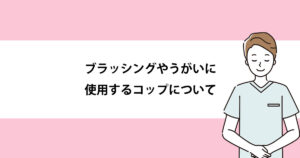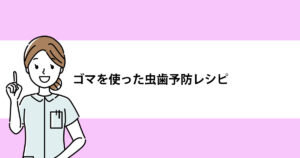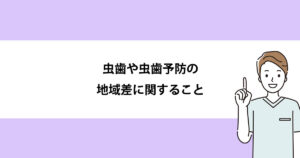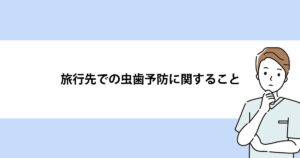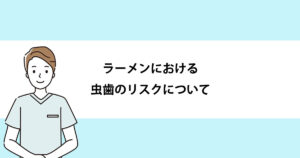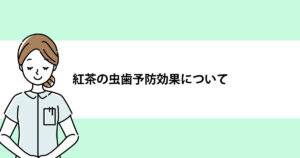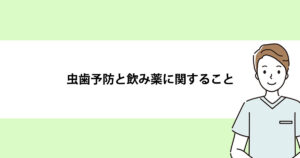虫歯予防の方法として真っ先に思い浮かぶものと言えば、毎日の丁寧なブラッシングですが、それと同じくらい食生活の改善も大切です。
また食生活の改善には、栄養バランスを整えることだけでなく、特定の食品を積極的に摂ることも含まれます。
今回は、虫歯予防としてナッツを摂取するメリット・デメリットを解説します。
虫歯予防としてナッツを摂取するメリット4選
虫歯予防の一環としてナッツを食べることのメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。
・虫歯菌のエサになりにくい
・歯を強化する
・唾液の分泌量が増える
・手軽に食べられる
各メリットについて詳しく説明します。
虫歯菌のエサになりにくい
ナッツは炭水化物の含有量が少ないため、虫歯菌のエサになりにくいです。
炭水化物は、体内で分解されて糖質になります。
虫歯菌は、こちらの糖質をエサにして酸をつくり出し、歯のエナメル質を溶かして虫歯を引き起こします。
また炭水化物は歯の溝や隙間に残りやすく、特に精製された白米などの炭水化物は唾液で分解されやすく、口内に長くとどまる傾向にあります。
ナッツはこれらのリスクが極めて少ないため、虫歯予防として食べるには適していると言えます。
歯を強化する
ナッツには、歯を強化して虫歯がつくられにくい環境を整える効果もあります。
特におすすめなのがアーモンドやクルミなどのナッツです。
これらはカルシウムやリンなどのミネラルが豊富に含まれていて、歯の表面のエナメル質を強化する効果が期待できます。
またナッツにはビタミンが豊富なものも多く、特に前述したアーモンドやクルミの他、ヘーゼルナッツやピスタチオなどに多く含まれています。
中でもナッツに多く含まれるビタミンB群は、虫歯菌の抑制や免疫力向上などの作用があり、ビタミンEには抗酸化作用や血行促進作用などがあります。
唾液の分泌量が増える
食べることで唾液の分泌量が増えるという点も、虫歯予防としてナッツを摂取することのメリットです。
ナッツはある程度硬さのある食べ物であるため、飲み込むにはしっかり咀嚼しなければいけません。
また咀嚼回数が増えれば増えるほど、口内で分泌される唾液の量が多くなり、虫歯の原因となる食べカスやプラークを洗い流しやすくなります。
さらに、唾液には抗菌作用や殺菌作用もあるため、ダイレクトに虫歯菌に抵抗することも可能です。
手軽に食べられる
虫歯予防は、基本的には半永久的に継続しなければいけません。
手軽に食べられるナッツは、虫歯予防の一環として非常に継続しやすいと言えます。
袋に入ったタイプのナッツは、そのまま取り出すだけで特に調理をせずに食べられます。
またチャック付きのものは、すべて食べきらなくても簡単に保存できます。
もちろん、カシューナッツ炒めなど、ナッツを料理に使用することもできます。
そのため、そのまま食べるのに飽きた場合でも心配は少ないです。
虫歯予防としてナッツを摂取するデメリット4選
前述したようなメリットがあるのに対し、虫歯予防としてナッツを摂取することには以下のようなデメリットもあります。
・カロリー、脂質が高い
・消化不良や便秘のリスクがある
・アレルギーのリスクがある
・歯にダメージを与える
各デメリットについて詳しく説明します。
カロリー、脂質が高い
ナッツはカロリーや脂質が高いため、食べすぎるとカロリーオーバーや体重増加の原因になることがあります。
また脂質が直接的に虫歯を引き起こすことはありませんが、肥満は糖尿病や高血圧といった生活習慣病のリスクを高めます。
これらの疾患は、虫歯や歯周病とも関連性が深いことで知られています。
消化不良や便秘のリスクがある
ナッツには、不溶性食物繊維が豊富に含まれています。
不溶性食物繊維は、水に溶けにくい食物繊維で、腸を刺激して便通を促す効果があります。
しかし、過剰に摂取すると便が硬くなり、便秘を引き起こすことが考えられます。
またナッツ類は脂質も多く含んでいるため、食べすぎると消化不良を引き起こし、下痢や胃痛の原因になることもあります。
アレルギーのリスクがある
ナッツにはアレルギーのリスクがあるため、虫歯予防として摂取する際は少量ずつから様子を見ましょう。
もしアレルギーを発症してしまったら、皮膚症状や粘膜症状だけでなく、呼吸器症状や消化器症状を引き起こすこともあります。
歯にダメージを与える
ナッツの中には、非常に歯応えがあるものも多いです。
1日数回食べる程度であれば問題ありませんが、何度も何度も食べていると少しずつ歯にダメージが蓄積し、かえって虫歯になりやすい環境をつくってしまいます。
まとめ
ナッツは栄養価が高く、虫歯を予防してくれる作用も数多く存在します。
しかし冒頭でも触れたように、虫歯予防を行うにあたっては、特定の食品を食べるだけでなく、栄養バランスを整えることも大切です。
そのため、「ナッツさえ食べておけば大丈夫」というわけではありません。
野菜や果物、肉や野菜など、多くの品目から多様な栄養素を摂取することを心掛けましょう。