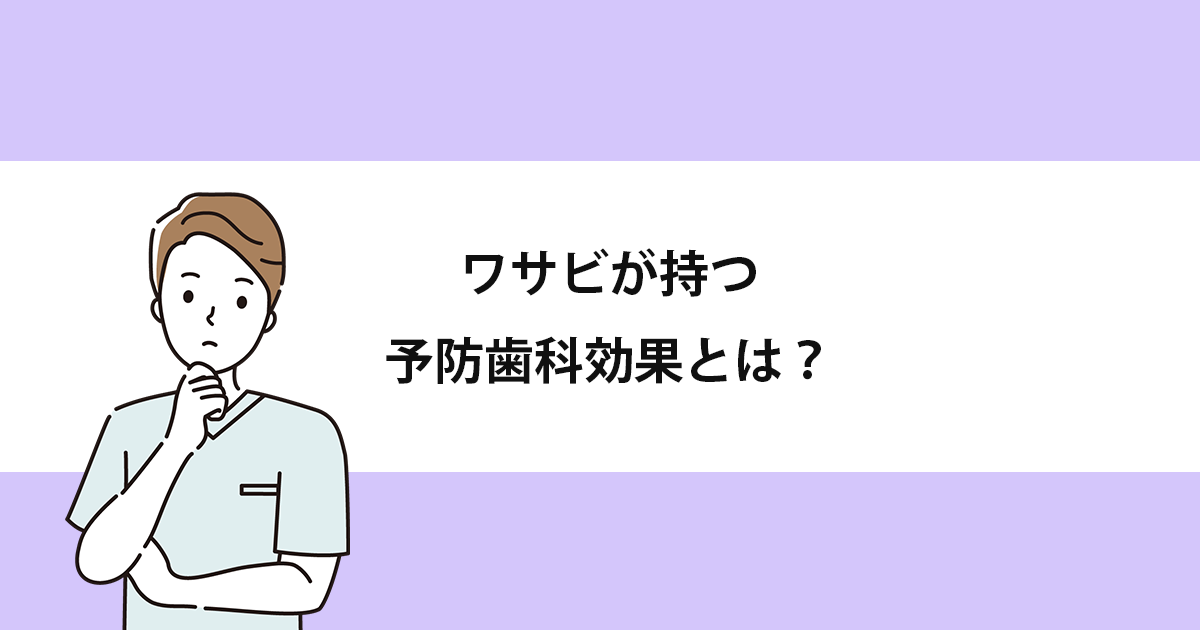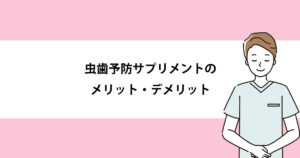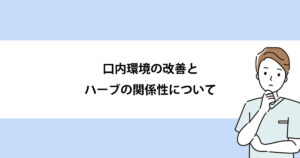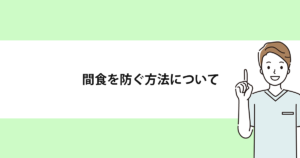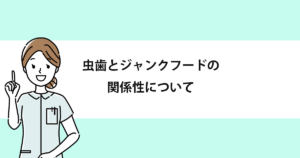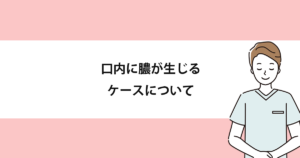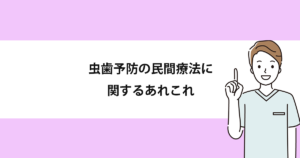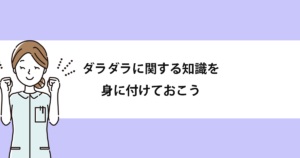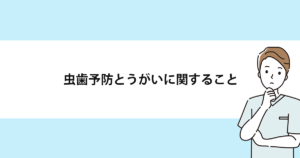予防歯科は、虫歯や歯周病など、さまざまな口内の疾患を未然に防ぐための取り組みです。
こちらは当然ブラッシングや、歯科クリニックでの定期検診も含まれますが、毎日摂取する食事によって疾患を予防するのも大切です。
今回は、ワサビが持つ予防歯科効果を中心に解説します。
ワサビの概要
ワサビをよく食べるという方はいると思いますが、どのようなものなのか理解していない方は多いのではないでしょうか?
ワサビは日本原産のアブラナ科の植物で、主に根茎をすりおろして薬味として利用される香辛料です。
ツンと来る辛味が特徴で、寿司や刺身などに添えられます。
日本では古くから薬草として利用され、江戸時代には寿司とともに広まりました。
ちなみに日本原産のワサビは本ワサビと呼ばれ、日本では西洋ワサビ(ホースラディッシュ)を加工したものが粉ワサビ、チューブ入りの練りワサビとして販売されています。
ワサビの予防歯科効果
あまり知られていないかもしれませんが、ワサビには以下のような予防歯科効果があります。
・殺菌効果
・口臭予防効果
・歯周病予防効果
・唾液分泌促進効果
各項目について詳しく説明します。
殺菌効果
ワサビには殺菌効果があり、こちらは虫歯菌や歯周病菌に対しても効果を発揮します。
ワサビに含まれるアリルイソチオシアネートは、天然の辛味成分であり、殺菌・抗菌効果を持つことで知られています。
水には溶けにくいですが、ほとんどの有機溶媒に可溶し、食品香料や抗菌・防カビ剤、忌避剤などの用途で使用されています。
またアリルイソチオシアネートは、口内で虫歯菌や歯周病菌が増殖するのを抑制する効果が期待できます。
口臭予防効果
ワサビには、口臭の予防効果もあります。
口臭を発する原因はさまざまですが、主な原因としては口内に蓄積したプラークや歯石が挙げられます。
プラークや歯石は、食べカスと細菌が混ざって塊になったものであり、中には大量の虫歯菌や歯周病菌が含まれています。
前述の通り、ワサビのアリルイソチオシアネートには殺菌作用があるため、口臭の原因となる細菌の数を減らしてくれます。
歯周病予防効果
歯周病予防効果も、ワサビが持つ予防歯科効果の一つです。
ワサビに含まれるフラボノイドは、植物に含まれるポリフェノールの一種であり、抗酸化作用や抗菌作用など、さまざまな生理活性を持つ天然化合物です。
7,000種類以上存在すると言われ、植物の色や苦味、香りなどに関わっています。
ワサビに含まれるフラボノイドは、イソサポナリンと呼ばれるもので、本ワサビの葉や茎に含まれています。
またフラボノイドには、歯周病の原因となる細菌の増殖を抑えたり、歯茎の炎症を抑えたりする効果が期待できます。
さらにビタミンCとフラボノイドを一緒に摂取すると、歯肉炎の改善効果が高まるという報告もあります。
唾液分泌促進効果
ワサビを摂取することにより、唾液の分泌量が増加します。
こちらは、ワサビの辛味成分による効果です。
唾液には口内の細菌を洗い流したり、酸を中和したりする働きがあるため、虫歯予防に役立ちます。
ワサビのその他のメリット
ワサビは予防歯科効果が期待できるだけでなく、他にもさまざまなメリットがあります。
ワサビの辛味成分は、唾液や胃液の分泌を促し、食欲を刺激したり消化を助けたりします。
また辛味成分は血液をサラサラにし、動脈硬化や高血圧などの予防に効果を発揮します。
さらにワサビの成分は、肝臓の解毒酵素を活性化させ、体内の有害物質を排出するのをサポートします。
ちなみにワサビの抗酸化作用やコラーゲン生成促進作用により、美白や美肌、シワ予防などのメリットを得られることもあります。
その他、毛乳頭細胞を活性化し、血流を改善できる効果があることから、育毛効果も期待できます。
こちらはフラボノイドの一種であるイソサポナリンの効果です。
ワサビを摂取する際の注意点
予防歯科の一環としてワサビを摂取する場合、食べすぎには注意が必要です。
ワサビの辛味成分であるアリルイソチオシアネートは、過剰に摂取すると舌の感覚を麻痺させ、味を感じにくくする可能性があります。
さらに辛味成分が胃腸を刺激しすぎると、腹痛や下痢につながることもあります。
またワサビをすりおろして食べる際は、食べる直前にすりおろすのがおすすめです。
一度すりおろしたワサビは、時間が経つと風味が落ちるため、早めに使い切りましょう。
ちなみに、ワサビの辛味成分は揮発性のものであるため、醤油に溶くと風味が損なわれます。
そのため、刺身や寿司に使用するときは、直接刺身にワサビをつけて食べるべきです。
まとめ
普段ただ単に好みでワサビを摂取していた方は、知らず知らずのうちに虫歯や歯周病を予防できていたということがわかります。
ただし本当の予防歯科は、多くの食品をバランス良く摂取することで初めて成立するものです。
またブラッシングなどのセルフケア、歯科クリニックでのプロフェッショナルケアも行わなければ、虫歯や歯周病に強い口内環境はつくられません。