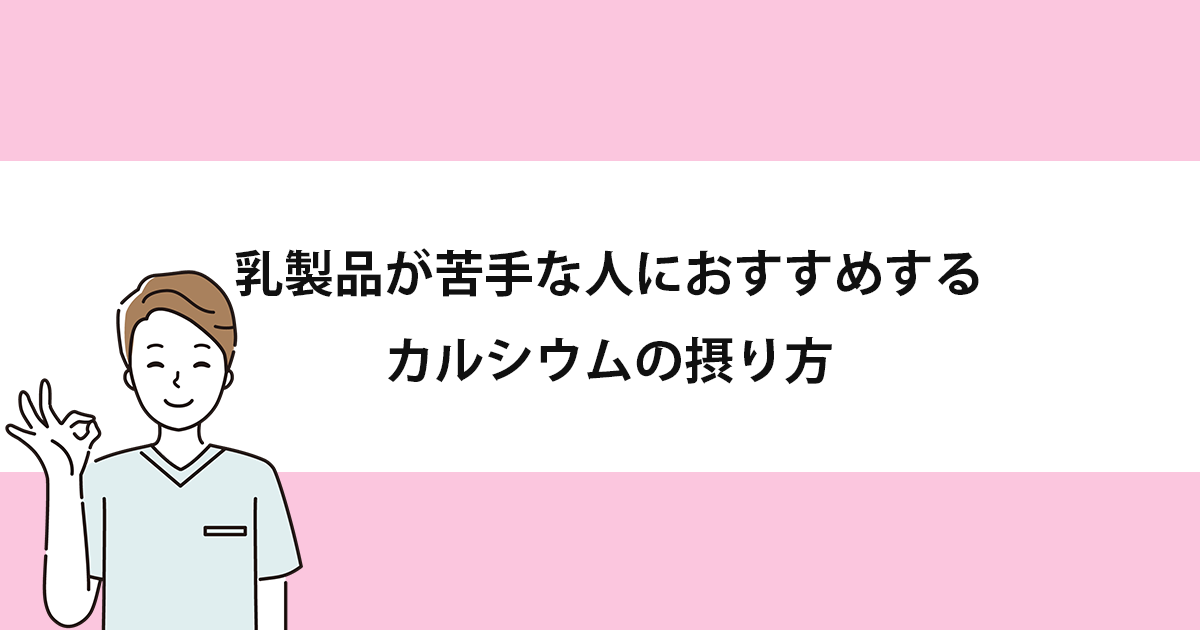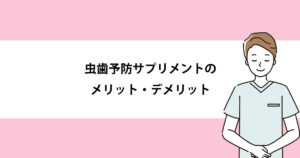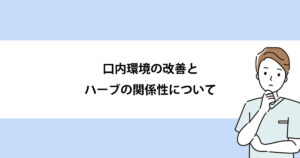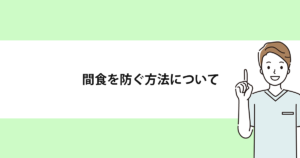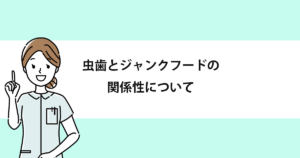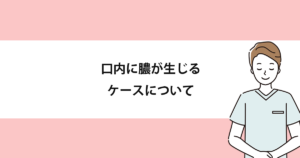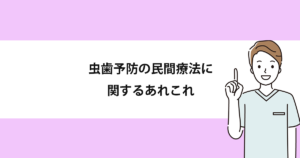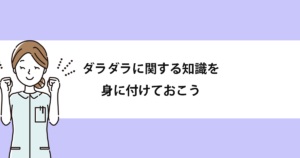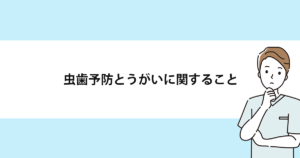丈夫な歯をつくるにあたって欠かせない栄養素の一つがカルシウムです。
またカルシウムが豊富な食べ物には、やはり牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品が挙げられます。
しかし、中には乳製品が苦手という方もいるでしょう。
今回は、乳製品が食べられない方におすすめするカルシウムの摂り方を中心に解説します。
カルシウムの予防歯科効果について
カルシウムには、以下のような予防歯科効果があります。
・歯のエナメル質を強化する
・再石灰化を促進する
・唾液の分泌を促す
カルシウムは歯の主要な構成要素であり、エナメル質を強くすることで酸による溶解を防ぎ、虫歯菌の攻撃から歯を守ってくれます。
また歯は酸によって溶けたり、唾液中のカルシウムやリンなどによって修復されたりを繰り返しています。
こちらの歯が修復される現象を再石灰化といいますが、カルシウムには再石灰化を促進し、初期虫歯を治してくれる効果があります。
さらに、カルシウムを十分に摂取できていれば、唾液の分泌量も増加します。
唾液の量が増えることで、再石灰化や自浄作用が上昇するため、虫歯のリスクを軽減できます。
乳製品が苦手な方におすすめするカルシウムの摂り方4選
乳製品が食べられない方は、以下の方法でカルシウムを摂取しましょう。
・野菜から摂取する
・海藻から摂取する
・小魚から摂取する
・大豆製品から摂取する
各項目について詳しく説明します。
野菜から摂取する
乳製品が苦手な方は、野菜からカルシウムを摂取する方法を試しましょう。
カルシウムが豊富な野菜の中には、癖が少なく食べやすいものが多いです。
例えば小松菜や菜の花、水菜といった野菜です。
特に小松菜は含有量が多く、1/4束ほどで119mgものカルシウムを摂取できます。
ちなみに、野菜を使った料理にもカルシウムが豊富なものはあります。
切り干し大根は中でもカルシウムが摂りやすいため、日々の食事に採り入れることをおすすめします。
海藻から摂取する
乳製品が食べられない場合、海藻からカルシウムを摂取する方法もおすすめです。
特におすすめなのはひじきで、こちらは煮物1食分10gにつき140mgものカルシウムを含んでいます。
そのため、前述した葉物野菜も苦手という方は、ひじきから摂取する方が確実に効率は良くなります。
小魚から摂取する
小魚も、乳製品が食べられない方がカルシウムを摂取できる食べ物としてはおすすめです。
ここでいう小魚とは、主にししゃものような小さな魚を指しています。
ししゃもの場合、3尾で149mgのカルシウムが含まれています。
一匹のサイズが小さいため、そこまで無理なくカルシウムを摂取できるのが魅力です。
また正確には小魚ではありませんが、素干しの桜エビもカルシウム源として魅力的な食品です。
大さじ1杯程度食べるだけで、100mgものカルシウムが摂取可能です。
大豆製品から摂取する
乳製品が食べられない方は、大豆製品からカルシウムを摂取する方法も試してみましょう。
特にカルシウムが豊富なのは、豆腐や納豆、厚揚げなどの大豆製品です。
豆腐は約1/2丁食べることで180mg、納豆は1パックにつき45mgのカルシウムが摂取できます。
また厚揚げについては、1/2枚食べることで240mgものカルシウムを摂り入れることが可能です。
ただし、厚揚げ1/2枚は約100gに相当するため、毎日摂取するのであれば納豆や豆腐の方が楽かもしれません。
食品からカルシウムを摂取する際のポイント
上記の食品からカルシウムを摂取する場合は、なるべく多くの食品を選ぶことが大切です。
例えばししゃもとひじき、豆腐と小松菜など、さまざまなジャンルの食べ物をバランス良く採り入れるようにしましょう。
またカルシウムの吸収率を上げるためには、ビタミンDもあわせて摂取しなければいけません。
ビタミンDは鮭やサンマ、キノコ類などに多く含まれています。
さらに、食べ方にも工夫が必要です。
ある程度噛み応えがある食品を食べる際は、なるべく長い時間噛むことを意識しましょう。
よく噛むことで唾液の分泌が促進され、口内環境が整います。
間食でカルシウムを摂取する場合は、砂糖が少ないものを選ぶのも大切です。
ちなみに、カルシウムの他にも積極的に摂取すべき栄養素は存在し、その一つにキシリトールが挙げられます。
キシリトールは、虫歯の原因となる酸の生成を抑制し、虫歯の進行を防ぐ効果があります。
こちらはキシリトール配合のガムやタブレットから摂取するのも良いですが、食品から摂取することも可能です。
主にイチゴやラズベリーなどの果物、ホウレンソウやカリフラワー、レタスやナスなどの野菜に多く含まれています。
まとめ
乳製品を一切食べられないという方であっても、カルシウムを摂取することは可能です。
もっともカルシウムの吸収率が良いのはやはり牛乳ですが、他のさまざまな食品を摂取すれば、同じくらいのカルシウムを摂取できます。
また予防歯科を極めるには、他の栄養素もバランス良く採り入れ、なおかつ適切なブラッシングや歯科クリニックでの定期的な検診も受ける必要があります。