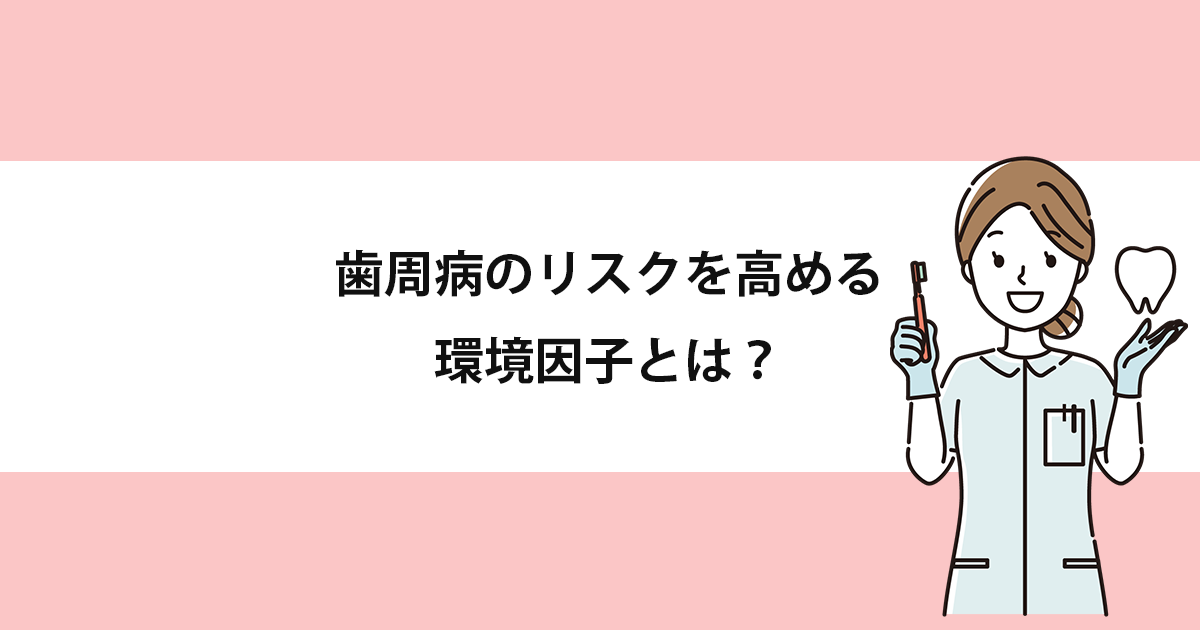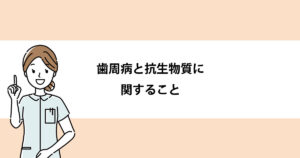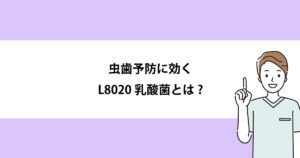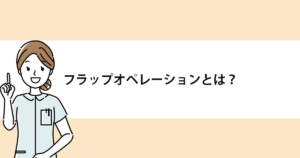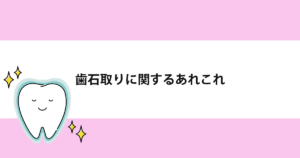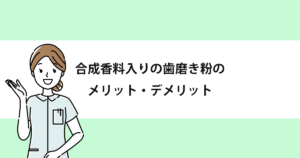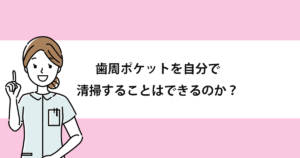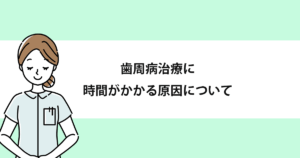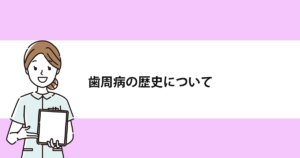歯周病には、リスクファクターというものが存在します。
こちらは危険因子とも呼ばれ、歯周病のリスクを高める要因のことを指しています。
またリスクファクターはいくつかの種類に分かれていて、そのうちの一つに環境因子があります。
今回は、環境因子の概要や詳細について解説します。
歯周病の環境因子とは?
環境因子は、人が生活する上で影響を与える物的・社会的な環境です。
簡単にいうと、患者さんが置かれている環境を指しています。
また歯周病のリスクファクターは、環境因子だけでなく微生物因子や宿主因子、生活習慣因子で構成されています。
微生物因子は、歯周病菌のことを指し、こちらに感染することで歯周病を引き起こします。
宿主因子は年齢や遺伝的要因、生活習慣因子は不適切なブラッシングや偏った食生活、睡眠不足などが該当します。
歯周病のリスクを高める環境因子7選
歯周病のリスクを上昇させる環境因子には、主に以下のものがあります。
・喫煙
・ストレス
・糖尿病
・骨粗鬆症
・薬剤
・噛み合わせ
・口腔習癖
各項目について詳しく説明します。
喫煙
喫煙は、歯周病のリスクを高める代表的な環境因子の一つです。
喫煙習慣がある方は、著しく歯周病を発症しやすくなります。
こちらは、タバコに含まれるニコチンが主な原因です。
ニコチンは血管を収縮させ、血流を悪化させる作用があるため、歯茎の免疫力が低下して歯周病菌の増殖を助長します。
ストレス
ストレスも、歯周病を引き起こす環境因子として挙げられます。
日々の生活でストレスが蓄積している方は、免疫力が低下しています。
免疫力が下がると、歯周病菌に対する抵抗力が弱くなり、発症のリスクが高くなります。
またストレスが溜まると、生活習慣が不規則になったり、ブラッシングなどのセルフケアをおろそかにしてしまったりするケースも増えます。
こちらはさらに歯周病のリスクを高める要因です。
糖尿病
歯周病のリスクを高める環境因子としては、糖尿病も挙げられます。
糖尿病は、歯周病と非常に関連性が深い疾患として知られています。
糖尿病を発症すると免疫力が低下し、ストレスが蓄積したときと同じように、歯周病菌への抵抗力が下がってしまいます。
また糖尿病を発症することにより、歯周病が進行しやすくなることも知られています。
糖尿病によって血管がもろくなると、歯茎の血流が悪くなり、歯周組織の修復に必要な栄養や酸素が十分に供給されません。
骨粗鬆症
歯周病のリスクを高める環境因子には、骨粗鬆症も挙げられます。
骨粗鬆症は、骨の量が減少し、骨がもろくなることで骨折しやすくなる疾患です。
骨の新陳代謝のバランスが崩れ、骨を壊す細胞が活発になる一方で、骨をつくる細胞の働きが追い付かなくなることが原因です。
また歯周病によって歯を支える歯槽骨が破壊されると、骨粗鬆症の影響でさらに歯周病の進行が早まることがあります。
薬剤
普段一部の薬剤を服用している方は、歯肉増殖症を引き起こし、歯周病のリスクを高めることが考えられます。
歯肉増殖症は、歯茎が正常以上に硬く膨らむ疾患で、薬剤の副作用が主な誘発要因として指摘されています。
歯茎の表面は弾力があり、歯と歯の間がぷっくりと腫れますが、痛みを伴わないのが特徴です。
ちなみに歯肉増殖症を引き起こす可能性がある薬剤には、てんかん治療薬や高血圧治療薬、免疫抑制剤などが該当します。
噛み合わせ
噛み合わせが良くないことも、歯周病のリスクを高める環境因子の一つに数えられます。
上下の歯の噛み合わせが悪い場合、歯に過剰な力がかかってしまい、その下の歯茎などの歯周組織にも負担がかかります。
そのため、すでに軽度の歯周病を患っている方は、症状が悪化するおそれがあります。
また噛み合わせだけでなく、歯ぎしりや食いしばりも歯周病の環境因子です。
歯ぎしりや食いしばりのとき歯にかかる力は、咀嚼をするときの数倍にものぼります。
これだけの力が日常的にかかり続けた場合、歯や歯茎などはなかなか正常な状態を保つことができません。
口腔習癖
口腔習癖とは、無意識に行われる口周辺での癖のことをいいます。
こちらも、歯周病のリスクを高める環境因子の一つです。
例えば口呼吸は、唾液の分泌を晴らし、口内を乾燥させます。
唾液には細菌を洗い流す自浄作用があるため、こちらの作用が低下すると歯周病菌は増殖しやすくなります。
また指しゃぶりについては、歯並びを悪くする原因の一つです。
特に前歯が前方に突出する出っ歯や、上下の歯が噛み合わない開咬といった不正咬合を引き起こしやすく、こちらは口呼吸を誘発するため、間接的に歯周病のリスクを高めます。
まとめ
しっかりブラッシングをしていれば、歯周病は予防できると思われがちですが、実際はさまざまな角度からケアをしなければいけません。
また歯周病を悪化させる環境因子については、ある程度患者さんが対策を取ることで、影響を受けにくくすることは可能です。
歯周病は世界一感染者数が多い感染症のため、徹底的にケアしなければ予防できません。