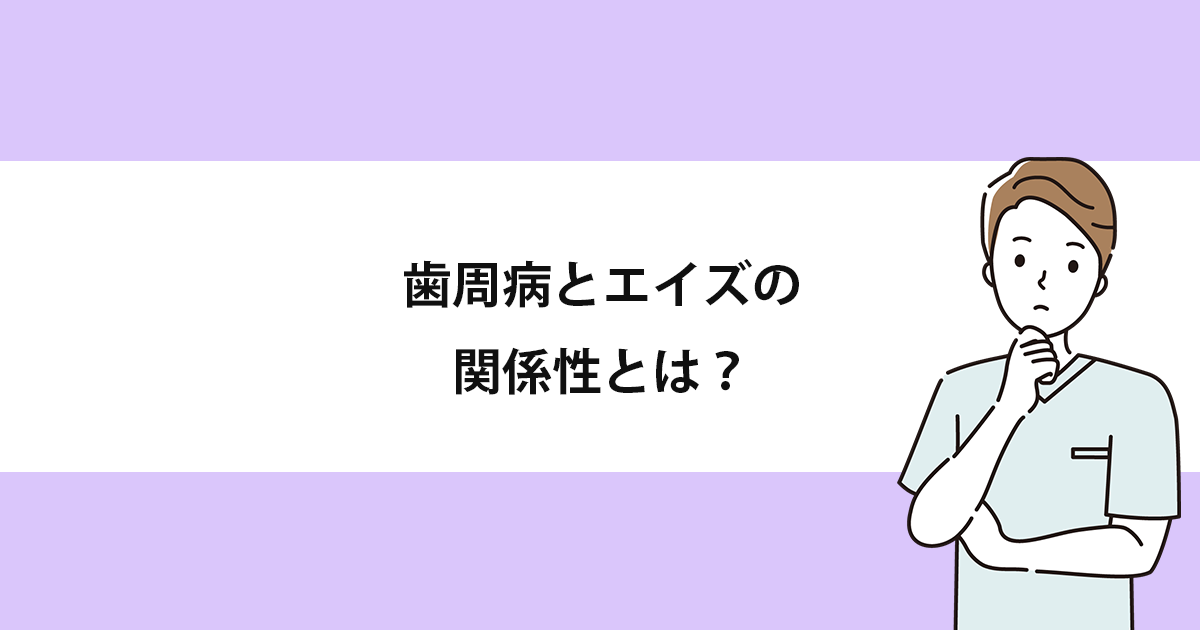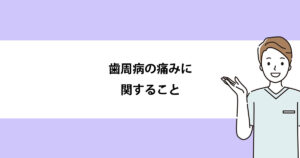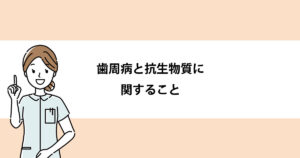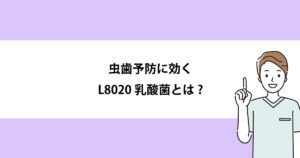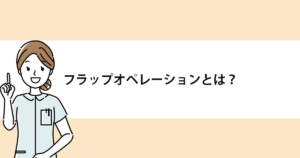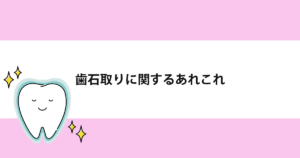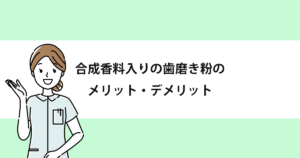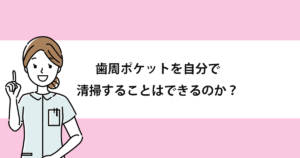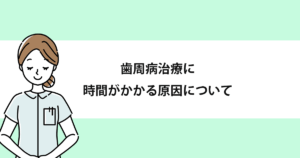歯周病の怖いところは、ありとあらゆる全身疾患との関係性があるところです。
またこれらの全身疾患の中には、ときに命を脅かすような疾患も数多く存在します。
その一つが、今回スポットライトを当てるエイズというものです。
ここからは、歯周病とエイズの関係性を中心に解説します。
エイズの概要
エイズは、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染することによって免疫力が低下し、健康なときにはかかりにくい疾患やがんにかかる状態をいいます。
よくHIVとエイズが混合している方がいますが、HIVは免疫の働きを司る細胞に感染し、破壊するウイルスの名前です。
エイズはそのウイルスに感染した状態のことであり、後天性免疫不全症候群とも呼ばれます。
またエイズは感染後、しばらくは症状のない無症候期が続きますが、数年~10年程度で少しずつ免疫力は低下していきます。
ちなみに現在では、エイズは不治の病ではなく、早期にHIV検査を受けて適切な抗HIV剤による治療を開始することで、発症を遅らせたり予防したりできます。
具体的には、ART(抗レトロウイルス療法)の進歩により、感染しても健康な方と同等の寿命を全うできる可能性があります。
ただし、HIVウイルスを完全に体内から排除することは困難であるため、生涯にわたって薬物療法と定期的な医療機関での受診が必要になります。
歯周病とエイズの関係性
HIVに感染することで発症するエイズは、歯周病と密接な関係があります。
具体的には以下の通りです。
・HIV活性化への影響
・歯周病重症化のリスク
・エイズの合併症のリスク
各項目について詳しく説明します。
HIV活性化への影響
歯周病を発症している方は、当然口内に大量の歯周病菌が存在しています。
また歯周病菌がつくり出す酪酸という物質は、HIVを活性化させる引き金になることが研究で示唆されています。
酪酸は、腸内細菌が食物繊維を分解してつくる短鎖脂肪酸の一種で、大腸の粘膜細胞の主なエネルギー源になるものです。
腸の健康維持を行うにあたってこちらの成分は必要不可欠ですが、前述の通り歯周病菌が産生する酪酸にはエイズ発症のリスクがあります。
歯周病重症化のリスク
エイズを発症することにより、歯周病が重症化するおそれもあります。
エイズになると身体の免疫力が低下し、歯周病菌への抵抗力も下がるため、当然症状は進行しやすくなります。
歯周病が重症化すると、歯茎の腫れや出血だけにとどまらず、歯の動揺が見られることもあります。
最悪の場合、歯が脱落することも考えられます。
一度抜け落ちた天然歯は、二度と元に戻ることはありません。
またエイズの合併症として歯周病や口腔カンジダ症が重症化し、その口腔状態からHIV感染に気付くケースもあります。
エイズ患者には、歯周病や口腔カンジダ症の他、特異な歯肉病変や口角炎など、多くの口腔症状が出ることが報告されています。
エイズの合併症のリスク
歯周病菌は、エイズの合併症であるカポジ肉腫を活性化する可能性も報告されています。
カポジ肉腫は、皮膚や粘膜、リンパ節や内臓など至るところに発生するがんです。
それに深く関与しているのが、カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスというものです。
またカポジ肉腫を発症すると、皮膚や口腔、喉の病変につながるだけでなく、リンパ浮腫や内臓病変も引き起こします。
さらにカポジ肉腫にも合併症が存在し、歯周病菌の数が多い歯周病患者の方はこちらのリスクも高まるとされています。
エイズを発症するデメリット
エイズは健康なときに発症しにくい疾患、例えばニューモシスチス肺炎やがんなどにかかりやすいというデメリットがあります。
また免疫力が低下した結果、肺炎や皮膚病、神経系の症状など、さまざまな症状が現れる可能性があります。
さらに免疫機能が極度に低下すると、最終的に脂肪に至る可能性もゼロではありません。
つまり、間接的に歯周病が死亡のリスクを高める可能性があるということです。
エイズを防ぐにはまず歯周病予防を
エイズの発症を防ぐには、まず毎日の丁寧なセルフケアで歯周病を予防し、口内の健康を維持することが大切です。
ブラッシングについては歯間ブラシやデンタルフロスも使用し、歯の表面や咬合面だけでなく、歯と歯の間や歯と歯茎の間までしっかりと磨きます。
またかかりつけの歯科クリニックに相談し、数ヶ月に一度定期的な歯科検診を受けることが推奨されます。
歯科クリニックでは、口内の状態から病状の進行を適切に評価し、専門的なメンテナンスを提供してくれます。
さらにすでにHIV陽性となっている方は、その旨を歯科医師に申告し、主治医と連携を取ることで安全かつ適切な歯科治療を受けることができます。
まとめ
歯周病は、一度発症すると完全に治すことが難しい疾患です。
症状が改善しても、日々生活する以上はいつでも症状が再発する可能性があります。
エイズも同じで、完全にHIVウイルスを排除するのは困難ですし、これらの疾患には相関関係があります。
いずれの疾患にも言えることは、発症の原因を詳しく把握し、リスクを高めないような行動を取ることです。